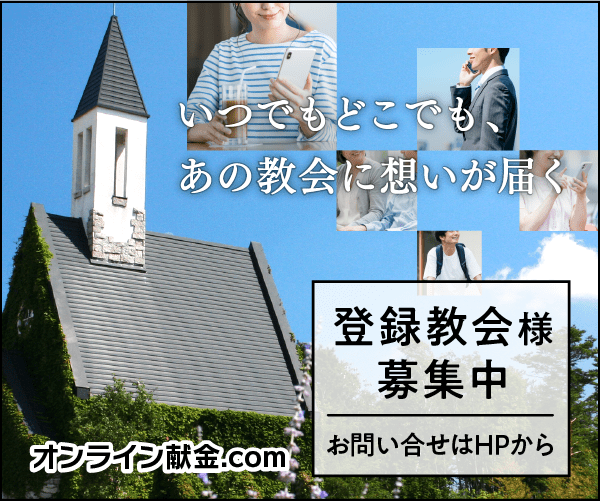チベット現代社会の婚姻をテーマとする映画『ラモとガベ(原題)』が公開された。冒頭で主人公のひとりガベがラモとの結婚届提出を試みると、本人の知らぬ間にガベが結婚していたと判明する。それは破談した過去の婚約に起因するが、元の婚約者は出家し尼僧院へ篭もっており、容易には離婚手続きが進まない。他方ラモは歌舞劇《ケサル王物語》のため稽古に取り組むが、私生活と舞台の両面で困難に直面する。
本作に一貫するのは、伝統的価値と近代秩序との相克をめぐる、チベット人監督ソンタルジャによる定点観測的な視座である。例えばガベが訪れる役所の壁には中国語文の標語が記され、届出用紙は漢字で書かれるのに対し、会話は主にチベット語方言で交わされる。ここでは中国語文が近代秩序を、漢語まじりのチベット語会話が浸食されゆく伝統的精神を否応なく象徴する。ガベが離婚手続きに苦労するのは、出家した元婚約相手にとってチベット仏教の戒律こそ俗世や国家秩序より優先されるからで、ガベの苦労を通して人間社会に普遍の今日的課題が浮かび上がる。家族をもつことは根源的な営為であるのに対し、国家の管理下に置かれた婚姻制度は近代以降の特殊態に実は過ぎない。各種の制度からなる社会システムの隙間を生き延びることを現代社会は人に強いるが、ウルリヒ・ベックの言う通り「人生を営むことは、このような条件下では、システムの矛盾を個々人の人生において解決していく営みとなる」。(ウルリヒ・ベック 『危険社会』)
一方、ラモが劇中劇で演じるケサル王の妃アタク・ラモは、生前の悪行から地獄へ落ちる。過去に秘密を抱えるラモには、このアタク・ラモの道行きが自身に重なり耐えがたい。100万以上の韻文詩からなるケサルの物語は、キルギスの《マナス》やモンゴルの《ジャンガル》と並び世界三大叙事詩ともされるが、高僧や役人を殺害し閻魔大王に裁かれるアタク・ラモの存在は、それでも妃を救い出そうとするケサル王の慈愛が讃えられるための道具立てに過ぎないともいえる。映画では公演当日、アタク・ラモが地獄から救い出される寸前に停電が起こり舞台は中断、客席から縁起が悪いと野次がとぶ。不吉さを覚えるラモは興行主へ再演を要求するが、不採算を理由に拒絶される。すべてが経済論理へ呑み込まれゆく現代、神事であった《ケサル王物語》の上演さえ。
ガベが小型トラックの荷台に載せた愛馬を、草原で解き放つ場面は印象的だ。キルギスの英雄叙事詩《マナス》を下地として資本主義世界に浸食される精神性を描く名作『馬を放つ』では、主人公の抱える抑圧や屈託が馬の解放という形で昇華される。しかし『ラモとガベ(原題)』においては、馬へ荷台から出るようにガベが促しても、追放を恐れるかのように馬は微動だにしない。キルギス同様に牧畜を主要な民族的アイデンティティとみなすチベットに出自をもつ監督の演出として、この描写は心に迫る。今日のチベットやモンゴル・中央アジアの映画や文学では、エンジンよりも馬を頼みとする遊牧民精神の誇りがしばしば描かれ、馬の野生と人の魂とが重なり合う。しかしガベの想いとは裏腹に馬自体が人間社会へ馴致(じゅんち)されきっており、ガベはもはや愛馬のたたずまいにすら己の希望を見出せない。
この場面で馬へ仮託するものの深さこそ監督ソンタルジャの白眉であり、世間には隠した顔として母の側面をもつラモの孤立を《ケサル王物語》が何ら救いあげない展開にもその手つきは通底する。伝統と近代の対峙というありふれた切り口が重要なのではなく、価値の画一化やジェンダーなど刻々変化する思潮への安易な還元を受けつけない全体性がソンタルジャ映画の語り口にはそなわっている。
ソンタルジャは前作『巡礼の約束』公開時の本紙インタビューにおいて、第4作となる本作および第5作の構想を語ってくれた。日本公開未定の新作では、江南を舞台とする父と子の物語が描かれるという。ソンタルジャが「チベット」を撮るのは出自からの必然に過ぎず、むしろ自ら起こした交通事故で母を失くした若い男の内面を巡礼の道に重ねるデビュー作『陽に灼けた道』以来、親と子の構図こそソンタルジャ映画全作を貫く原風景といえそうだ。
“父と子の物語”から直ちに想い起こされるのは、チベット高原の辺境部に生きる家族を捉えたソンタルジャ第2作『草原の河』の主人公である幼い娘の父親と祖父との関係性である。文革後家族を捨てて僧侶となった祖父は映画に登場するものの、その顔が映されることはない。
『ラモとガベ(原題)』においても、出家した元婚約者の尼僧をカメラは捉えず、数度に及ぶガベとの会話は声のみで表現される。チベットやヴェトナムなど大乗仏教圏に限らず、ミャンマーやタイなど上座部仏教圏においても広範にカメラを僧侶へ向けることへの忌避は元来強いが、それだけが理由とはむろん考えられない。これを筆者は以前「隠された祖父の顔に集約される個を超えた時間性」(下掲インタビュー記事より抜粋)の表現と受けとめたが、本作鑑賞後の今となってはさらに考察を進める必要があるだろう。隠される部分の存在により、顕わとなる部分はさらに鮮明度を上げるという面もあり、古来から顔の秘匿を通した聖性の獲得は宗教藝術表現の一典型だ。
さて、チベットを舞台とする映画は少なくないが、そのほとんどは長らく外国人監督によるものだった。チベット人監督作が日本で劇場公開されたのはわずかに3年前、ソンタルジャ監督第2作『草原の河』が初となった。第3作『巡礼の約束』の昨年公開に続き、『ラモとガベ(原題)』はソンタルジャ第4作となる。インド亡命へ至るダライ・ラマ14世の前半生を描くマーティン・スコセッシ監督作『クンドゥン』や、その14世のラサ時代をドイツ人登山家の視点から描くジャン=ジャック・アノー監督作『セブン・イヤーズ・イン・チベット』など、1990年代のチベット関連映画は外部視点から大上段に構えるものが目立った。
これに対し2000年代以降はチベットカモシカの乱獲を背景とする陸川(ルー・チュアン)監督作『ココシリ』や五体投地での聖地巡礼を描く張揚(チャン・ヤン)監督作『ラサへの歩き方~祈りの2400km』など、より質実なテーマが選ばれるようになる。これには中国映画市場の開放に伴う中国人監督の活躍が影響しており、2010年代チベット人監督の台頭はこうした潮流の尖端に位置づけられる。
こうした流れは今日、チベットのみならず世界的に観測される。新型コロナ流行を奇貨とする動画サイト主導の映画業界再編により、非欧米圏の若い世代への製作費投資は加速するさなかにある。ハリウッドの牙城が崩れつつある現在でも世界の主要国際映画祭はいまだ欧米に集中するものの、チベットや中央アジア、アフリカや大西洋・太平洋島嶼部など、注目すべき沃野は広大だ。
一昨年の第20回東京フィルメックスにおいて最優秀作品賞を獲得し今年日本公開された『羊飼いと風船』(原題『气球』)のペマ・ツェテンらと並び、ソンタルジャは目下チベット映画監督第一世代を牽引する。彼らが精力を尽し表現するのは、もはや政治的に記号化され消費の対象となる型通りの「チベット」ではなく人間そのもの、重層的で多義的な一つの小宇宙に他ならない。
(ライター 藤本徹)
『ラモとガベ(原題)』 “拉姆与嘎贝” “Lhamo and Skalbe”
公式サイト:http://moviola.jp/tibet2021/
4月2日(金)まで岩波ホールにて上映中ほか全国巡回上映中。
参考引用文献:ウルリヒ・ベック 著、東廉 伊藤美登里 訳『危険社会: 新しい近代への道(叢書・ウニベルシタス)』(法政大学出版局、1998年)
関連言及記事など
『羊飼いと風船』
輪廻転生のチベット仏教宇宙を生きる夫が、市場経済に攫われるなか堕胎を迷う妻に「爺ちゃんが生まれるんだぞ、殺す気か」と迫る。
チベット映画を牽引する多産型巨匠と化したペマ・ツェテン/Pema Tseden。稀有の進化系を辿りゆく感性は、崑崙を超え中央アジア大草原をも包み込む。 pic.twitter.com/zYVsLYQuBr
— pherim⚓ (@pherim) January 25, 2021
中国、その想像力の行方と現代 新作映画ジャ・ジャンクー『帰れない二人』、フー・ボー『象は静かに座っている』にみる表現の自由と未来 2019年11月27日