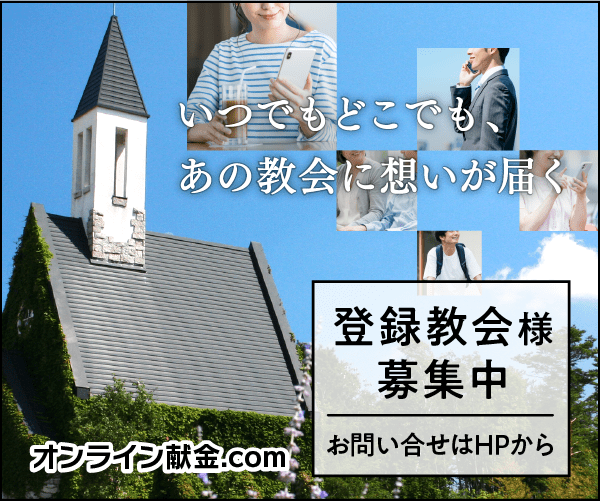世俗の時代へのオランダ人の対策
これまでのところバーフィンクの論点は、あくまでも当時のオランダにおける問題であったように見えるかもしれない。「19世紀オランダの説教者の説教が下手だったのは、自らの生きる19世紀オランダ人の性質について批判的な目が足りなかったからだ」というわけだ。しかしながら、バーフィンクが自らの時代のオランダについて行った批判を、今日、強い影響力を持つ論説に照らして読むとき、バーフィンクの批判が及ぶ範囲は一気に拡大する。
カナダの政治哲学者チャールズ・テイラーは、『世俗の時代』(邦訳なし、2007年、ハーバード大学出版局)において、ヨーロッパ社会が経験した中世から近代への著しい変化の過程を説明している。つまり、「神を信じないこと」など想像できなかった中世から、それが想像できるばかりか、神を信じなくても社会への完全参加を拒まれることなどない近現代の世俗的な西欧への変化だ。これは間違いなく、現代に生きる私たち全員に関わる物語なのだ。
「近代西欧人の自我に生じた重大な変化こそ、このような世俗化への過程をもたらしたもの」という指摘が、テイラーの多岐にわたる見識の中で最も重要だ。テイラーの論点を簡潔に述べよう。
「中世ヨーロッパの人々は、神や世間が自我に影響を与えることを妨げるような、険しく通ることのできない壁の存在を想像することはなかった。中世における自我とは、むしろ『浸透性の』ものであり、自我は、他者、世間、神と絶え間なく通い合うものだった。自我は、周囲からの刺激に常に影響されるものだったのだ。中世の人々は、自らの身体、環境、神を、世俗化した子孫たちとは違ったかたちで経験していた」。テイラーによれば、近代人は「距離を置いた自我」意識を発達させたのだ。
世俗化した近代人の自我は、自分を超えたものとは区別され、大きな影響を受けない。つまり、「(自我の内側にある)心と(外側にある)世の中」を分ける考え方、あるいは(一個人の中の)「心と体」さえも異なるものであるとする考え方は、近代人にとっては普通のことだ。病気になったり失業したりして、「私はこんなことの影響を受けはしないぞ」と誰かに告げるとき、近代人は、「(周りの状況から)隔絶され、それに影響されない自我」というものを想像している。
こうした考え方は、中世の祖先たちには理解できないだろう。(テイラーはこの近代的な自我を「肉体を離れた自我」という印象的な表現で呼んでいる)。神と私たちを隔てるこうした諸々のものや距離が私たちと神との間にあるから、神が遠くに感じられるのは言うまでもない。テイラーによれば、世俗化は、人間が「距離を置いた自我」という意識を持って初めて可能となる。
現在のところ、近代人のあり方に関するテイラーの説明は圧倒的に説得力があり、広い範囲に適用できる。19世紀後半のオランダのような急速に世俗化する社会で生きる人々の自我が、「浸透性の」ものから「距離を置いた」ものへと進化するのを、私たちはテイラーの壮大な語りのうちに見るだろう。当時の人々の多くが理解できる例えとして、ポットヒーテルの「おねむのジョン」をバーフィンクが借用したことは、当時の文脈では、まさにこのパロディが的を射ていたことを表しているといえよう。
自我の性質の変化が説教に与えた影響についてバーフィンクが唱えた説は、19世紀オランダという特定の場所と時代に関するものだった。しかし、テイラーのより大きなナラティブ(語り)を背景としてこの変化を評価しようとするとき、その意義は著しく増す。そう、19世紀オランダの説教者は、同時代のオランダ人の性質への批判力が十分でなかったから説教が上手にできなかったのだ。
しかしながら、『世俗の時代』に照らして考えるならば、こうしたオランダ人の国民性は、もっとずっと大きな兆候がある一つの地域に現れたものと考えられる。大きな兆候とは、西欧社会で広く進んでいる自我の世俗化であり、今日私たちが知っている社会の誕生だ。
バーフィンクが正しいとするなら、モダニティー(近代性)が出現したことは、当時も今も、説教にとってはよいことではなかった。近現代人にとっては一般的に、国を問わず、説教を上手にすることは難しいことだ。なぜなら、私たちの持っているモダニティーは、神や福音によって心をかき乱されることを阻むものだからである。それに対して私たちの祖先は、私たちよりもずっと神や福音が自分の心に影響を与えることを許していた。(次ページに続く)
「クリスチャニティー・トゥデイ」(Christianity Today)は、1956年に伝道者ビリー・グラハムと編集長カール・ヘンリーにより創刊された、クリスチャンのための定期刊行物。96年、ウェブサイトが開設されて記事掲載が始められた。雑誌は今、500万以上のクリスチャン指導者に毎月届けられ、オンラインの購読者は1000万に上る。